K画伯は、遅い昼食を済ませると、アトリエのソファーに身を沈めた。居間の方から、赤ん坊の泣き声がしている。画伯の娘が初孫を抱いて里帰りしているのだ。
「あの児の魂はどこから来て、どうしてこの児に宿ったのだろう。それはもしかしたら今は亡き両親の生まれ代わりかも知れない。この児の運命や如何に」
画伯はそんなことを考えていた。両親の願いに反して画業に転じた彼は、自身の半生を振り返る時、どうしても「運命とは何か」を考えることが多かったのだ。しかし、未だその解答は得られていなかった。また、そんな彼の周囲にも自身の運命と闘っている人々が少なからず居たのだが、運命について満足な解答を持つ者は居なかった。
「あの児の魂はどこから来て、どうしてこの児に宿ったのだろう。それはもしかしたら今は亡き両親の生まれ代わりかも知れない。この児の運命や如何に」
画伯はそんなことを考えていた。両親の願いに反して画業に転じた彼は、自身の半生を振り返る時、どうしても「運命とは何か」を考えることが多かったのだ。しかし、未だその解答は得られていなかった。また、そんな彼の周囲にも自身の運命と闘っている人々が少なからず居たのだが、運命について満足な解答を持つ者は居なかった。
午睡のお供にと、今日は高校時代の「倫理・社会」の教科書を携えた。適当に頁をめくると、イギリスの経験哲学者ロックの肖像と標題が目に付いた。
「人間は生まれたとき白紙である」
彼はその頁を開いたまま眠りに落ちると、夢を見始めた。
「人間は生まれたとき白紙である」
彼はその頁を開いたまま眠りに落ちると、夢を見始めた。
夢の中でK画伯は、真白いキャンバスに向かっていた。傍らには絵の具のチューブが転がっていた。通常ならそれらのラベルには、シルバーホワイトとかアイボリーブラックとかセルリアンブルーとか、色彩の名前が書いてあるのに、今それらのチューブには「DNA」とか「蛋白質」などと書いてあった。画伯はそれらの絵の具を絞って下絵を描き始めた。更に「理性」、「欲望」、「意志」などのチューブを搾って描き込んだ。絵の具の塊は次第に人間の姿となり、鼓動し呼吸し胎動を始めた。次第に自立性を増し、ついにそれは自我意識を獲得して動き始めた。その人物は四角いキャンバスの中に居て、「何故、私がこんな狭いところに生まれたのだ、息が詰まる、ここから出してくれ」と叫び始めた。画伯は、次の白いキャンバスを画架に掛けると、今度は絵の具を薄めて描き始めた。ローランサンの絵のような淡い人物が姿を成すにつれ、そこにも自我意識が芽生えた。それはキャンバスの底辺に跪いて、自分の薄幸の理由を執拗に問うのであった。次の白いキャンバスには、モルタルのように絵の具を厚く盛り上げて描いて行った。ルオーの絵のような重厚な人物が姿を成すと、その表面には亀裂が走り、目や鼻が剥離し落下し始めた。その人物は強烈な自我意識に震えながら、「何故、俺が、こんな病気になる運命なのだ!」と悲嘆の叫びを上げたのだ。画伯は次々と人物を描いて行き、アトリエは様々な人物像で一杯になった。それぞれの人物像はそれぞれの境遇を嘆き、その運命と対峙しながら、敢え無く壊れ去るのであった。
再び赤ん坊の泣き声がして、K画伯は午睡から目を覚ました。そうだ、ここにも、新たな生命の誕生に続いて、新たな魂の形成が始まっていたのだ。彼は忽然と理解した。画伯の運命論の誕生であった。それは、「誰かの魂があの世から来て、何かの理由によって特定の個体に宿る」のではなくて、「魂は、個体の発生の後に、その中に経験の塊として新たに生じるものである」ということだ。だから、その魂は必然的に、自身の容器である個体の来し方行く末に違和感を覚えて、自分の運命を嘆くようになるのだ!こうしてK画伯は、周囲の人々がそれぞれの運命と闘うことになるメカニズムを理解したのだった。
しかし、この午睡の夢物語は、「画伯自身がその個体に宿った理由」を教えるものではなかった。「何故、画伯が19xx年という年にこの家に生まれ、画家をしているのか」という問いに答えるものではなかった。ふと画伯はシュルレアリスムの芸術家マルセル・デュシャンの墓碑銘を思い出した。
「死ぬのはいつも他人ばかり」
そうか!「他人の死」と「自分の死」は別物である様に、「他人の運命」と「自分の運命」も、その発生のメカニズムが異なるのだ。
画伯は、得られそうに見えた解答が再び扉を閉ざしたのを感じ、いつもの嘆息をつきながら、描きかけのキャンバスに向かうのであった。(平成23年7月31日)
八戸地区弘前大学医学部同窓会誌「はちのへ」 第43号 掲載
「死ぬのはいつも他人ばかり」
そうか!「他人の死」と「自分の死」は別物である様に、「他人の運命」と「自分の運命」も、その発生のメカニズムが異なるのだ。
画伯は、得られそうに見えた解答が再び扉を閉ざしたのを感じ、いつもの嘆息をつきながら、描きかけのキャンバスに向かうのであった。(平成23年7月31日)
八戸地区弘前大学医学部同窓会誌「はちのへ」 第43号 掲載
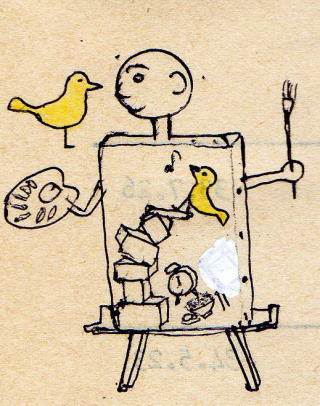 |