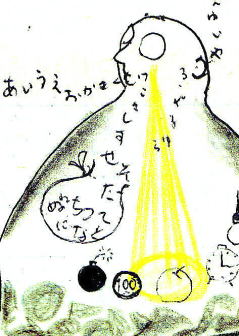西暦20××年、K博士は人生の大半を費やして、あらゆる学問を修めた。彼の体の中には厖大な知識の断片が際限なく蓄積されていた。彼は何時もこう言うのだった。
「正確な知識というものは、こちらが操作を加えずとも、自らの属性によって互いに手と手を取り合い結びつき、独りでに完成を目指すものだ。」
彼はこの事を「知識の結晶作用」と呼んでいた。それは、貯蔵された良質の食材から、芳醇な美酒が醸造されて来るのに似ていた。そんな恵みを、熟年の日々の大きな楽しみとしていたのである。
彼の知的行動の一例を見てみよう。彼はある時期「応用化学」の勉強に没頭し、一応の理解に到達すると、「我が内なる底なし沼へ沈め!」と念じて嚥下の仕草を繰り返し、その勉強を終えた。 その次の時期には、研究生として某医大に通い詰め、「内蔵学」の勉強に励んだのである。そしてその内容を把握すると、「我が内なる底なし沼へ沈め!」と念じて嚥下の仕草を繰り返し、その勉強を終えたのである。このようにして、彼はそれぞれの知識を彼の「アイデアのるつぼ」である「底なし沼」へ沈めてしまい、意識の上から忘れ去るのであった。そうして数ヶ月が過ぎた頃、この「底なし沼」へ記憶の糸を沈めて慎重に手繰り上げると、必ずや何か全く新しいアイディアがその糸に巻き付いて浮上するのであった。彼はこの場合、「人工臓器」に関するいくつかの新しい技術を思いつき、特許申請に及んだのであった。
ある日、K博士は日課の散歩に出た。初老を迎えた彼の足もとは、相当危うくなっていた。突然、彼は坂の上でつまずき、もんどり打って転げ落ちながら、逆さになってやっと静止した。体の奥底で何か居心地の悪さを感じるや否や、何者かが彼の口から転がり出た。驚いたK博士は、その得体の知れない者に向かって、「お前は何者じゃ!」と叫んだ。その者は、「わしは底なし沼の主(ぬし)じゃ」と、返答した。そしてその者は続けて言った。
「わしは、無意識という大きな底なし沼の暗闇に棲み、そこに降り注ぐストレスという毒性沈殿物を食べて生きる、沼の主じゃよ。あんたという生き物の本当の主はこのわしなんじゃよ。あんたというものは、この底なし沼の水面に漂う浮き草のようなものなんじゃよ。あんたは常時そこに浮かんでいて、沼の水面下から、知識の結晶の他に何か変な物でも湧き出て来やしないかと、それが自分を勝手に突き動かして馬鹿をやらかすんじゃないかと、心配ばかりしている。それを例えれば、スーパーで買って食べた弁当がひょっとして腐っていて、そのうち嘔気が突き上げて来るんじゃないかと不安がるのとそっくりじゃ。
じゃが安心せい、わしが居る。人生を生きていれば、当然不愉快な事がしばしばある。あんたがそれらをぐっと嚥下してしまえば、それがこの沼に沈降して来るのじゃ。わしは、それらの中に歪みとして閉じ込められた有害な力を溶解してやっておるのじゃ。例えて言えば、極限まで引き絞られた弓がつがえた矢も放たずそのまま沈んで来るようなこともあれば、満たされることのない空虚な器も沈んで来る。わしは、それもこれも皆この腹に入れて消化して来たのじゃ。毒物が肝臓で解毒されるように、わしが精神の解毒をしとるのだ。あんたの見果てぬ夢など、凡人には体の毒じゃ、早く忘れるが身のためじゃ」
K博士は、この思わぬ出来事を不愉快に思い、傍らに落ちていた棒きれを掴むや否や、力の限り振り回して、この沼の主を追い払ってしまった。そうして何事もなかったかのようにして帰宅すると、日々の多忙な生活へと戻ったのであった。
しかし、K博士は今まで何ともなかった事がストレスとなったまま、消化も中和もされずに蓄積され、次第に中毒症状を呈して来たのだ。計算の早い彼にとって、「あの沼の主と決別すべきか仲良くすべきか」の結論を出すのに時間は要らなかった。
彼は、あの主を小声で呼び寄せ、いきなり取り押さえると、無我夢中で呑み込んでしまった。それは、彼の体の奥底へ沈潜して行った。それとともに、再びK博士は自分自身が思うに任せないような、自分が何者かに突き動かされているような変な気持ちに戻ったのだった。
彼は、あの主を小声で呼び寄せ、いきなり取り押さえると、無我夢中で呑み込んでしまった。それは、彼の体の奥底へ沈潜して行った。それとともに、再びK博士は自分自身が思うに任せないような、自分が何者かに突き動かされているような変な気持ちに戻ったのだった。