K爺さんは、この頃言葉が出て来ない。年齢のせいだと思いながらも、いや何処か違うと考えるうちに、突然大変な事を思い出したのだ。それは、「言葉には限りがある」という事なのだが、これには少し説明が要る。
K爺さんが小学生だった頃に遡ってみよう。彼はその頃、実はとてもお喋りな子供だった。ある朝、学校の朝礼で、校長先生のお話があった時だ。彼は例によって生半可にお話を聞くうちに、忽然と妙な理解をしてしまったのだ。
それはこういう事だった。人は体の中に「言葉の小袋」というものを持っていて、その中には「あ、い、う、え、お」から「ん」までの平仮名がたくさん入っていて、それらを口から吹き出すことで、相手に気持ちを伝えることが出来る。だから、サイフの中のお金と同じで、言葉を無駄に使うと、早く無くなってしまうので、大事に使いなさい、という事だった。一瞬子供は目を丸くした。
それはこういう事だった。人は体の中に「言葉の小袋」というものを持っていて、その中には「あ、い、う、え、お」から「ん」までの平仮名がたくさん入っていて、それらを口から吹き出すことで、相手に気持ちを伝えることが出来る。だから、サイフの中のお金と同じで、言葉を無駄に使うと、早く無くなってしまうので、大事に使いなさい、という事だった。一瞬子供は目を丸くした。
その平仮名を好きなように使って来たK爺さんは、今頃になってこんな奇妙なお話を思い出してしまい、当惑の他はなかった。子供の頭は仕様がないものだと思ってみたものの、事態ここに至ればこのお話は案外本当のことかも知れないと、結構こころが揺れたのである。そろそろ自分の平仮名が尽きる?K爺さんは再び目を丸くした。
一体わしの平仮名たちはどこへ行ったのだろう。大概のものは風に吹かれてシャボン玉のように流れ去ってしまった。それに乗って、あの頃の胸の高鳴りもどこかへ行ってしまった。今になって思う、それらの平仮名を紙上に書き留めて置くべきだったと。古今東西、文字を書く人々の願いは同じなんだ。生まれて初めて、日記か何か書いてみようと思った。
彼の放ったある平仮名は、誰かの心に棘のように突き刺さったままかも知れなかった。逆に、K爺さんのこころに入って来た美しい平仮名もあった。それは例えば、妻の「あ、な、た」だったり、誰かさんがつぶやいた「ひ、み、つ」だったりしたのだ。
彼の放ったある平仮名は、誰かの心に棘のように突き刺さったままかも知れなかった。逆に、K爺さんのこころに入って来た美しい平仮名もあった。それは例えば、妻の「あ、な、た」だったり、誰かさんがつぶやいた「ひ、み、つ」だったりしたのだ。
無情にも、彼の「小袋」は次第に枯渇していった。彼には尚更に言葉が貴重なものと成っていった。ある難病の患者さんは、進行性の筋肉の萎縮によって全身の筋力を失いながら、最後に残された指先の力を使い、コンピュータのキーボードを押して言葉を紡いだと言う。その患者さんは、
「言葉が勿体なくって、人の悪口なんか言っていられませんよ」
と、液晶画面に字を並べたという。更に増悪して指の筋力も失うと、介助の人に「あ、い、う、え、お」を順に言って貰い、必要な平仮名のところまで来ると瞬きを返して、言葉を拾ったという。
「言葉が勿体なくって、人の悪口なんか言っていられませんよ」
と、液晶画面に字を並べたという。更に増悪して指の筋力も失うと、介助の人に「あ、い、う、え、お」を順に言って貰い、必要な平仮名のところまで来ると瞬きを返して、言葉を拾ったという。
K爺さんは、ある友人が、ご臨終の時「あ、あ、あ、う、う、う」とばかり唸って他界したのを思い出した。今のK爺さんにすれば、
「あいつはやはり生前、半端な事ばかり言う奴だったからな」
と、妙に合点が行くのだった。
K爺さんは、今まさに平仮名が尽きようとする最期に、自分の「小袋」を振り払って、残りの平仮名を全て並べてみた。彼は、「あ、り、が、と、う」の五文字を遺して、息を引き取った。
「はちのへ医師会のうごき」 平成16年 8月20日 422号に掲載

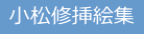
「言葉の小袋」を見る

「あいつはやはり生前、半端な事ばかり言う奴だったからな」
と、妙に合点が行くのだった。
K爺さんは、今まさに平仮名が尽きようとする最期に、自分の「小袋」を振り払って、残りの平仮名を全て並べてみた。彼は、「あ、り、が、と、う」の五文字を遺して、息を引き取った。
「はちのへ医師会のうごき」 平成16年 8月20日 422号に掲載
「言葉の小袋」を見る
